我が家もおふたり様に該当するので、手に取ったのが
「おふたりさまの老後」は準備が10割
元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え
まだ両親が、健在ですがこれからのことを考えてどうすればよいのか
さらに私たち自身もどうしていくべきかを考えさせられます。
いまさらながらLifePlanの検討や資産の棚卸をせねばと思っています。
最後に記載していますように、事前準備が大事ですね。
はじめに
第一章 実は夫婦だけではすまない「相続」問題
Q1 夫の財産は妻が全部相続できますか?
夫の親族にも相続の権利があります。(前妻の子供も含む)
Q2 法定相続人って、誰のことですか?
配偶者、子供、孫(直系卑属) 親(直系尊属) 兄弟姉妹(傍系血族)
Q3 相続では、財産はどう分けられますか?
法定相続分の割合が決まっているが、話し合いで自由に決められる。
Q4 相続財産が2000万円あります。相続税はかかりますか?
2025年現在は3000万円+法定相続人の数✖600万から必要
我が家は、4200万円 配偶者控除 1億6000万円
Q5 おふたりさまの相続は、どんなパターンが考えられますか?
①妻がすべて相続する
②兄弟や両親がいて遺産がいらないと言う
③兄弟や両親がいて遺産が欲しいと言う
Q6 遺産分割協議書にサインしてもらえない場合はどうすればいいですか?
家庭裁判所で調停
Q7 どうやって連絡を取ればいいですか?
戸籍をたどって現住所を調査もしくは専門家に力を借りる
第2章 おふたりさまには「遺言書」必須です!
Q8 残された配偶者にすべての財産を渡すためにはどうすればいいですか?
遺言書を書くことで配偶者に100%財産を残すことができる。
Q9 遺言書さえあれば、配偶者は本当にすべての遺産を受け取れますか?
兄弟姉妹に遺留分がないので、親亡き後は配偶者が100%となる。
子供があるときは、遺留分を請求されることがある。
Q10 ふたりとも亡くなった場合、遺言を実行してくれる人は誰ですか?
遺言書に「遺言執行者」を指定しておく
遺言執行者の業務は、以下の通り
①遺言執行者になったことを相続人に通知する
②遺言の内容を相続人に通知する
③被相続人の相続財産調査を行い、相続材策目録を作成し
相続人に交付する
④遺言書の内容を実行し、完了後に相続人に報告する
Q11 遺言執行者って、誰に頼めばいいの?
甥や姪などの親族、士業の専門家
遺言執行者の指名に強制力はない(事前に了承をもらう)
Q12 法定相続分通り相続させたい場合でも、遺言書をつくったほうがいいですか?
相続の結果が変わらない場合でも、遺言書があったほうがスムーズ
遺言書は個人からの最後の贈り物
Q13 「法的に有効な遺言書」って、どんなものですか?
自筆証書遺言 公正証書遺言のふたつがある
Q14 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、どちらがいいですか?
自筆証書遺言・・・いつでもどこでも無料で書き直し修正ができる
ただし、手書きで不備があると無効
公正証書遺言・・・公証役場で保管されるので盗難の恐れが恐れがない
手間と費用が掛かり、2名の証人が必要(相続人以外)
Q15 「公正証書遺言」って、どうすればつくれますか?
専門家に準備を手伝ってもらう方がよい
費用 5000万から1億の場合 4万3千円
Q16 遺言書には、何を書けばいいですか?
財産の関することだが、付言事項として思いを記載できる
遺言事項 ①財産②身分③遺言の執行
第三章 相続&遺言の「こんなときはどうする?」を解決
Q17 自分が亡くなり、妻も亡くなった後自分の甥に
残したい財産があるのですが…
財産を引き継ぐ順番まで指定したいのであれば、信託という方法
Q18 「家族信託」とはどういう制度ですか?
財産を信頼できる親族に託し、管理してもらう
管理する権利だけを他の人にお願いする。
公正証書で契約を結ぶ。
Q19 血のつながりがないけれど、お世話ににあった人に
財産を残したいのですが…
→寄贈という方法。生前に渡す場合は贈与
贈与は贈与税、寄贈は相続税となる。
Q20 遺産を寄付したいときは、どうすればよいですか?
遺言書に記載する。
Q21 全財産を配偶者ではなく、甥や姪に残すことができますか?
遺言書にその旨を記載すればよいが、配偶者に遺留分は必要なため
生前に配偶者に相談しておくほうがよい
Q22 別居しているDV夫に遺産を渡したくないのですが…
相続排除という方法。
DVなどの事実を明らかにして、被相続人の戸籍のある市町村役所に
廃除届を提出する。
ただし、家庭裁判所に申し立てて、認めてもらう必要がある。
夫婦の場合は離婚すれば、相続人でなくなる。
Q23 「生命保険」をかけていますが、保険金は相続の対象になりますか?
死亡保険金は、相続財産とはみなされない。
相続税の支店では、相続税が課される。(500万✖相続人人数分は非課税)
Q24 「生命保険」が相続対策になるというのは本当ですか?
契約者・被保険者・受取人の関係で変わってくる。
Q25 おふたりさまの遺言書は何歳くらいで書いておけばいいですか?
考えが変わったら書き換えられるので、早すぎることはない。
新しい遺言書が優先される。
Q26 おふたりさまの場合は、夫が遺言書を書けば安心ですか?
お互い作成するほうが良い。
Q27 遺言書の内容は、配偶者に内緒にできますか?
相続人は「利害関係者」なので、公正証書遺言の作成には立ち会えない。
Q28 「妻に財産をすべて残す」という遺言書を書いたけど、
妻が先に亡くなったらどうなりますか?
死亡した相続人への遺言の効力はなくなる。
予備的遺言・・妻が先に亡くなった場合は・・・
Q29 自宅が亡くなった夫の名義のまま。どうしたらいいですか?
出来るだけ早く、新しい名義に変更する。
Q30 実は前妻との間に子供がいるのですが、このまま黙っていても
よいでしょうか?
黙っていても相続時に子供の存在はわかる。
離婚していようと、別居していようと自分の子供は相続人
Q31 突然、亡くなった妻の親せきから遺産相続の相談を受けました。
そのようなケースもあるので、しっかり内容確認。
Q32 個人に借金がある場合の相続は、どうしたらいいですか?
事前に財産の状態を整理し、相続する人が早めに判断できるようにする。
①すべての相続財産を相続する。単純承認
②プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する。限定承認
③プラスもマイナスも放棄する。相続放棄
第四章 配偶者が亡くなって「おひとりさま」になったら頼れるのは誰?
Q33 身元保証とはなんですか?
就職・高齢者施設入所・病院入院などに必要な本人以外の誰かの保証
Q34 施設入所や入院の際の身元保証人の役割は何ですか?
緊急時の連絡先、支払いが滞った時の保証、亡くなった時の費用清算
荷物の引き取り
Q35 おふたりさまの場合、お互いが身元保証人になることができますか?
可能なケースもあるが、高齢や亡くなった時のことを考えておく。
Q36 おふたりさまの身元保証人は誰に頼めばいいですか?
身元保証人サービス・・・民間企業、一般社団法人、NPO法人、弁護士等
Q37 介護や支援が必要になったばあいは、どうしたらよいですか?
まずうは、地域包括支援センターに相談。(介護・医療・保険・福祉など)
Q38 地域包括支援センターでは、どんなことを相談できますか?
65歳以上の人に対して、必要な差サービスや制度の紹介
デイサービス・介護保険の申請
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談
・包括的、継続的ケアマネジメント
Q39 将来認知症になったら、いろいろ困りごとがありそうで心配です。
判断力が低下するので、本人判断や確認手続きに支障が出る
Q40 認知症になったら、預金が引き出せなくなるって本当ですか?
判断力が十分でなければ、口座が凍結される恐れがある。
条件がクリアできれば、家族が引き出せる場合がある
Q41 「成年後見制度」について教えてください。
後見人が被後見人を保護し、財産管理など様々な判断を行う制度
Q42 誰が後見人になるのですか?
任意で決める任意後見と裁判所が決める法定後見
Q43 「成年後見人制度はやめておいたほうがいい」と聞いたことがあるのですが
①財産管理に厳しい制限がある
②いったん開始すると原則としてやめられない
③費用が掛かる(後見人や後見監督人への報償)
Q44 認知症になってしまった場合、後見人制度以外の財産管理方法はありますか?
家族信託(財産を管理する人と利用する人を分けられる)
Q45 自分が死んだ後の様々な手続きが気になります。
死後事務委任契約の活用
Q46 「死後事務任意契約」ってなんですか?
未払いの費用の清算、葬儀・埋葬の手配、死後に発生する手続きを委任
Q47 「死後事務委任契約」は誰にお願いすればいいですか?
遺言執行者、行政書士、司法書士など
第五章 おふたりさまの老後の住まい方
Q48 家にため込んだたくさんの荷物。老後に片づけられるでしょうか?
体力・気力が十分なうちが勝負。60歳前後
早めの片づけが、人生を豊かにする。
Q49 家財整理って、何からはじめたらいいですか?
使うものだけを残す。(使えるものではない)
Q50 亡くなった配偶者のパソコンやスマートフォンはどうすればいいですか?
重要なデジタル情報の有無を確認する。
デジタル就活
①PCやスマホのログインIDとパスワード
②ネット銀行やネット証券の口座情報
③サブスクリプションの課金サービス情報
Q51 自宅に高齢者だけで住みつづけるのは難しいですか?
外部のサービスを使って補いながら自宅で生活
介護保険を使って訪問介護による生活サポートや民間サービス
シルバー人材センターや見守りサービス
Q52 配偶者がいなくなってからの一人暮らし、何もかも自分でやれるか不安です。
生活力(社会的な手続きやお金の管理など)をつけておく
必要最小限のことはお互い教えあったり、必要な情報をまとめる
Q53 自分よりもペットがながいきしそうで、先のことが不安です。
飼い主は最後までペットについて責任を持つ義務がある。
知人や団体を探すもしくはペット信託を利用する。
Q54 都会と田舎、老後の暮らしにはどちらが向いていますか?
それぞれ「人間関係」がポイント
都会 人間関係が機能的 田舎 人間関係が濃厚で全人格的
Q55 住み慣れた自宅の「家じまい」はどうしたらよいでしょうか?
まずは家財の処分から実施。
空き家の放置はデメリットばかり。
Q56 自宅はあるけど、貯蓄があまりなくて不安です。
リースバック 自宅を売却して賃貸物件として家賃を払う
ただし、売却がやすくなりやすい。
家賃が払えないと退去しなければならない。
リバースモーゲージ 自宅を担保に融資を受ける
都市部などの資産価値の高い物件に限られる
借入額がそれほど大きくない
契約者が死亡時に自宅を売却しなければならない
Q57 住み慣れた我が家と高齢者施設、老後の住まいはどちらがよいでしょうか?
健康状態や希望に合わせて住まいを決める
元気なうちに高齢者施設の見学をしておく
Q58 高齢者施設へ入所することになったら、事前にどんな準備が必要ですか?
①身元保証人の依頼
②どの施設に入所するかの選定
③引っ越し
Q59 種類や区部悦がよくわからない高齢者施設。選び方を教えてください。
経済状況や本人の状態(要支援、要介護)に合わせて検討
自立型もしくは介護型
公的施設か民間施設か
①特別養護老人ホーム 要介護3以上 安価で待機者が多い
②介護老人保健施設 要介護1以上 原則3か月
③介護療養型医療施設 要介護1以上 常に医療が必要な方
④軽費老人ホーム(ケアハウス) 要介護1以上 身寄りのない自立が不安な人
⑤介護付き有料老人ホーム 介護度に合わせて費用負担
⑥住宅型有料老人ホーム 介護は外部サービスの選択制
⑦グループホーム 認知症で要支援2以上
⑧サービス付き高齢者住宅 安否確認や生活相談のサービスで
食事や介護は別途契約
⑨シニア向け分譲マンション 富裕層向け家事支援があるが介護は外部サービス
①~④は公的施設 ⑤以降は民間施設 ⑧⑨は自立している人向け
退去要件 どの程度の状態になったら退去しなければいけないのかを確認
第六章 おふたりさまの終活。葬儀・お墓についても考えておこう
Q60 手元にあるエンディングのーと、なかなか書けないのですが・・・
記載例)
①財産や保険に関する情報
②家族への思いやメッセージ
③これまでの人生の総括
④医療や介護についての希望
⑤葬儀やお墓に関する希望
⑥連絡先リスト
⑦IDやパスワード
⑧遺言・相続についての希望
書きやすい部分だけでも書いてみる
ただしエンディングノートは遺言でないので、法的効力はない
Q61 延命治療をしてまで長生きしたくないのですが・・・
その意思をしっかり伝えておくことが大事
いざというときに自分の意思を伝えられない可能性がある
尊厳死宣言公正証書
①病状が不治であり、死期が迫っている際には、延命処置を拒否すること
②尊厳死は本人の希望であり、石含めた医療従事者に刑事上・民事上の
責任を問わないこと
③苦痛の緩和に関する処置を望むこと
④精神が健全な状態の際に本人が撤回しない限りは、この宣言は有効であること
Q62 葬儀は誰も呼ばないでおこうと思っていますが、構いませんか?
身内だけの家族葬にするとか通夜や葬儀を行わずに火葬のみを行う直葬とする。
Q63 自分や配偶者が亡くなったら家族葬にしたいと思っていますが
後悔はしないでしょうか?
費用を抑えられるが、参列者が少ないため香典も少なくなる
葬儀に呼ばれなかったとしての不満や「故人に線香をあげさせてほしい」と
自宅に弔問客が来るケースがある。
Q64 お墓ってよくわからないんですが、どんな種類がありますか?
①市町村などの地方自治体(公営墓地)
②お寺などの宗教法人(寺院墓地)
③墓地を経営する公営法人(民間霊園)
Q65 承継者のいないおふたりさまがは入れるお墓って、ありますか?
永代管理付きの納骨堂や合葬墓など承継の必要ないお墓
Q66 永代管理って、どういうことですか?
費用を一括で支払い、一定期間管理をしてくれる
Q67 死後、遺骨は海に撒いてほしいのですが・・・
一定のルールを守れば海に還ることができる
パウダー状に粉骨するなど
Q68 「墓じまい」って、何から手を付けたらよいのでしょうか?
①名義の確認・変更
②墓地の返還とお墓の解体工事
・墓地の返還に関する届け出(墓地返還届)
・お墓の解体に関する届け出(墓地工事施工届)
・お骨の移動に関する届け出(改葬許可申請)
③石材業者への依頼
おわりに
これから老後の準備に向き合うすべてのおふたりさまへ
事前に備えるからこそ、いざというときに最善の策がとれる
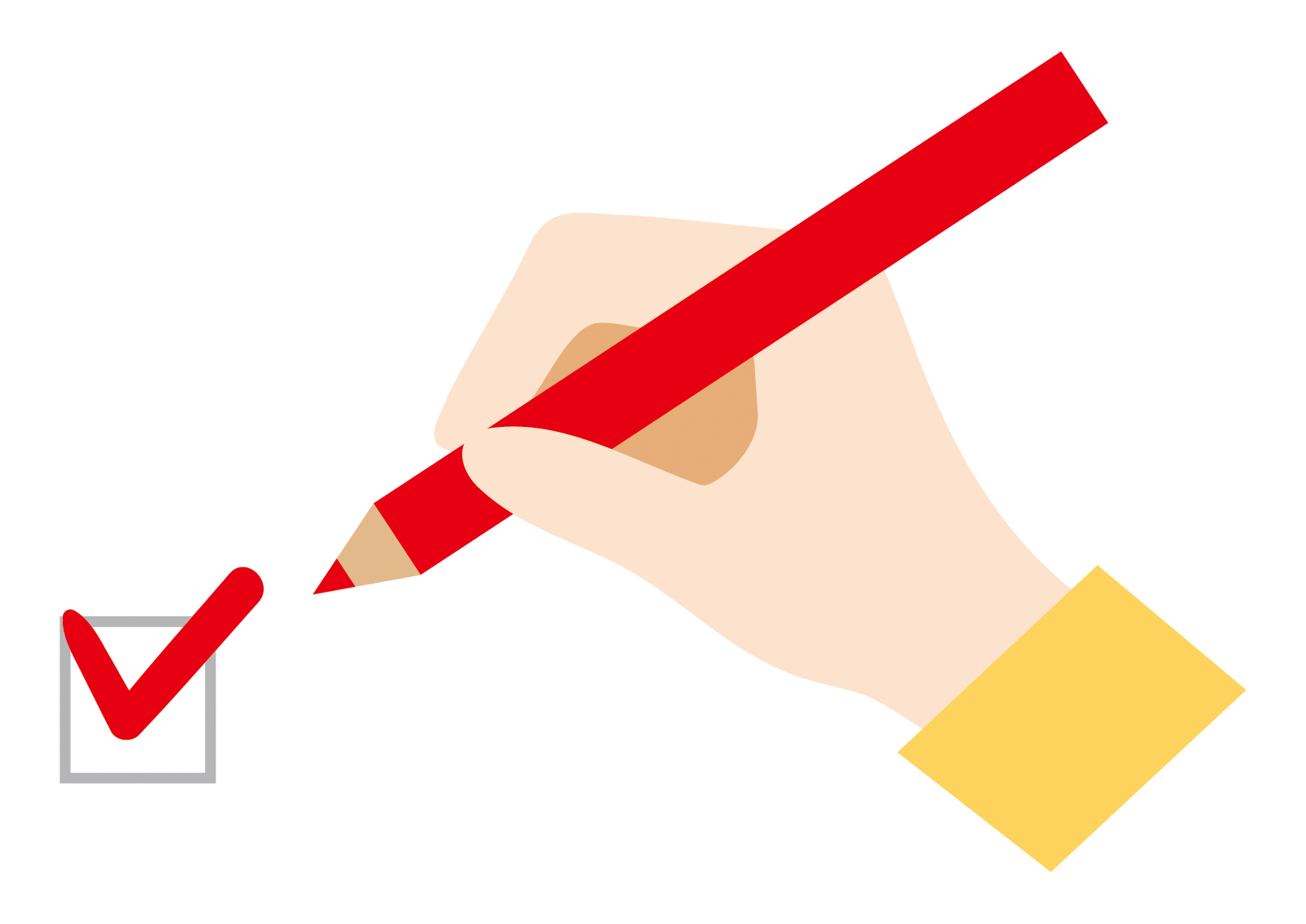

コメント